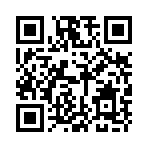WBSS(ワールド・ボクシング・スーパーシリーズ)バンタム級トーナメント開幕戦
WBA世界バンタム級王者・井上尚弥vs元WBAスーパー王者・現WBA同級4位ファンカルロス・パヤノ
横浜アリーナ 2018.10.7
なんだ、これは。
世界のボクシング史において、
ここまでの衝撃的な結末があっただろうか。
ヘビー級のような重量級においては、
ワンパンチで試合が終わるということは珍しくない。
しかし、
ここはリミット53.5キロの世界である。
井上尚弥のパンチの破壊力はケタ違いだ。
まともにヒットせずとも、
かすっただけでもぶっ倒してしまう。
パヤノは十分に作戦を練って井上対策をしてきたはずだ。
あのパンチをもらわないために、
まずは井上のスピードを上回ること、
そして踏み込ませないだけの距離をとること、
ここを意識していたはずなのだ。
緊張感が漂うファーストコンタクト、
互いのリードジャブが交錯する。
前回のマクドネルとは違う雰囲気、
変則的なサウスポーを相手に苦戦するのではないか。
ここから数秒後、
信じられない光景が広がっていく。
井上が左ジャブを突き刺した後、
右ストレートがそことは違う角度で放たれた。
パヤノの顎から上へと、
アッパーの軌道を描いた右ストレートがパヤノの顔面をえぐった。
両足で踏ん張っていたはずのパヤノが、
スローモーションのようにゆっくりと後ろに倒れていく。
なんだ?
なにが起こったんだ?
この事態を理解するまでに数秒の時間を要した。
繰り返すが、
パヤノは両足で踏ん張っていたはずだ。
普通であれば踏ん張りがきいてダウンは免れることができる。
ここで、
なぜ倒れてしまうのだ。
試合の終盤、
スタミナも消耗し、ダメージが蓄積された状態であれば理解できる。
しかし、
これは試合の序盤、
井上のファーストパンチがヒットしたにすぎない。
かつて、
バンタム級には一撃で相手を倒すチャンピオンがいた。
山中慎介。
「神の左」と称された左ストレート。
ただ、
これは大きなモーションから繰り出される渾身の左ストレートである。
これと比べて井上のパンチはどうだ?
前回のマクドネル、今回のパヤノ、
いやスーパーフライ級の頃からそうだった。
小さなモーションから繰り出した軽めのフックでさえ、
当たれば相手は一発でのびてしまう。
井上の拳に触れたらもう終わり。
今までに、
スーパーフライ級~バンタム級で、
こんな拳を持つボクサーがいただろうか。
いや、
これはバンタム級の拳を超越している。
2階級上、
フェザー級の王者とも真っ向から打ち合えるんじゃないか。
全盛期のロマゴンだって、
ここまでのインパクトは残していない。
世界のボクシング界を、
一人の日本人が震撼させている。
これは強すぎる。
WBSSでなければ、
誰だって井上との試合は避けるだろう。
WBSSに出場できた井上には運がある。
これはトーナメントだ。
否応なしに、
他団体の王者と拳を交えることができる。
真の世界最強を求める男にとって、
こんなにありがたい話はない。
準決勝、決勝と、
またあっさりと一撃で仕留めてしまうのではないだろうか。
相手が他団体王者だろうが、
無敗の王者だろうが関係ない。
井上の拳がかすっただけで十分。
そこで試合は終わってしまう。
井上は強すぎる。
凄すぎるよ。
勝手に夢を描いてしまうが、
今回のWBSSバンタム級で優勝したら、
次はスーパーバンタム級に上げてほしい。
そして、
井上が階級を上げた年にWBSSスーパーバンタム級トーナメントが開催される流れになって、
そこでも優勝してもらいたい。
今は世界王者が乱立する時代である。
WBAスーパー王者、正規王者、WBC、IBF、WBO、
場合によっては各団体に暫定王者もいるわけだから、
1つの階級に5本以上のベルトがある計算になる。
そこに加えて王者になれば、
強い相手との対戦を避けることも可能となってしまう。
これでは誰が真の世界最強なのかがわからない。
これはつまらないことだよ。
全階級でWBSSをやればいいのだ。
4団体王者がトーナメントで戦えばいい。
本当に強い男同士で戦って、
真の王者を決めればいい。
今はただ、
井上尚弥が世界中の誰もが認める最強王者になる日を心待ちにしている。
WBA世界バンタム級王者・井上尚弥vs元WBAスーパー王者・現WBA同級4位ファンカルロス・パヤノ
横浜アリーナ 2018.10.7
なんだ、これは。
世界のボクシング史において、
ここまでの衝撃的な結末があっただろうか。
ヘビー級のような重量級においては、
ワンパンチで試合が終わるということは珍しくない。
しかし、
ここはリミット53.5キロの世界である。
井上尚弥のパンチの破壊力はケタ違いだ。
まともにヒットせずとも、
かすっただけでもぶっ倒してしまう。
パヤノは十分に作戦を練って井上対策をしてきたはずだ。
あのパンチをもらわないために、
まずは井上のスピードを上回ること、
そして踏み込ませないだけの距離をとること、
ここを意識していたはずなのだ。
緊張感が漂うファーストコンタクト、
互いのリードジャブが交錯する。
前回のマクドネルとは違う雰囲気、
変則的なサウスポーを相手に苦戦するのではないか。
ここから数秒後、
信じられない光景が広がっていく。
井上が左ジャブを突き刺した後、
右ストレートがそことは違う角度で放たれた。
パヤノの顎から上へと、
アッパーの軌道を描いた右ストレートがパヤノの顔面をえぐった。
両足で踏ん張っていたはずのパヤノが、
スローモーションのようにゆっくりと後ろに倒れていく。
なんだ?
なにが起こったんだ?
この事態を理解するまでに数秒の時間を要した。
繰り返すが、
パヤノは両足で踏ん張っていたはずだ。
普通であれば踏ん張りがきいてダウンは免れることができる。
ここで、
なぜ倒れてしまうのだ。
試合の終盤、
スタミナも消耗し、ダメージが蓄積された状態であれば理解できる。
しかし、
これは試合の序盤、
井上のファーストパンチがヒットしたにすぎない。
かつて、
バンタム級には一撃で相手を倒すチャンピオンがいた。
山中慎介。
「神の左」と称された左ストレート。
ただ、
これは大きなモーションから繰り出される渾身の左ストレートである。
これと比べて井上のパンチはどうだ?
前回のマクドネル、今回のパヤノ、
いやスーパーフライ級の頃からそうだった。
小さなモーションから繰り出した軽めのフックでさえ、
当たれば相手は一発でのびてしまう。
井上の拳に触れたらもう終わり。
今までに、
スーパーフライ級~バンタム級で、
こんな拳を持つボクサーがいただろうか。
いや、
これはバンタム級の拳を超越している。
2階級上、
フェザー級の王者とも真っ向から打ち合えるんじゃないか。
全盛期のロマゴンだって、
ここまでのインパクトは残していない。
世界のボクシング界を、
一人の日本人が震撼させている。
これは強すぎる。
WBSSでなければ、
誰だって井上との試合は避けるだろう。
WBSSに出場できた井上には運がある。
これはトーナメントだ。
否応なしに、
他団体の王者と拳を交えることができる。
真の世界最強を求める男にとって、
こんなにありがたい話はない。
準決勝、決勝と、
またあっさりと一撃で仕留めてしまうのではないだろうか。
相手が他団体王者だろうが、
無敗の王者だろうが関係ない。
井上の拳がかすっただけで十分。
そこで試合は終わってしまう。
井上は強すぎる。
凄すぎるよ。
勝手に夢を描いてしまうが、
今回のWBSSバンタム級で優勝したら、
次はスーパーバンタム級に上げてほしい。
そして、
井上が階級を上げた年にWBSSスーパーバンタム級トーナメントが開催される流れになって、
そこでも優勝してもらいたい。
今は世界王者が乱立する時代である。
WBAスーパー王者、正規王者、WBC、IBF、WBO、
場合によっては各団体に暫定王者もいるわけだから、
1つの階級に5本以上のベルトがある計算になる。
そこに加えて王者になれば、
強い相手との対戦を避けることも可能となってしまう。
これでは誰が真の世界最強なのかがわからない。
これはつまらないことだよ。
全階級でWBSSをやればいいのだ。
4団体王者がトーナメントで戦えばいい。
本当に強い男同士で戦って、
真の王者を決めればいい。
今はただ、
井上尚弥が世界中の誰もが認める最強王者になる日を心待ちにしている。
WBC世界バンタム級タイトルマッチ
ルイス・ネリvs山中慎介
2018・3・1
一夜明けてからも、ネリの体重超過の問題が物議を醸している。
前回の試合、ただでさえドーピング疑惑で世間を騒がせていたのだ。
汚名を挽回するためにも、今回の試合に向けてのコンディション調整はいつも以上に慎重に行うべきであったはず。
これはネリだけの問題ではない。
ネリ陣営全体の問題である。
ボクシングはケンカではない。
試合が終われば、互いに笑顔で健闘をたたえ合う。
これこそがボクシングの素晴らしさなのだ。
試合前日に行われた計量の時点において、両者のコンディションには大きな開きがあった。
極限にまで体重を絞ってきた山中と、肉体に余裕を持ったままのネリ。
ボクシングがなぜ階級制をとっているのか。
それは体重差が(1階級の)1.8キロあるだけでもパワーが別次元のものとなるからだ。
計量時、山中とネリの体重差は2キロ以上あった。
また、極限にまで絞った状態から食事をとり試合までに体重を増やしていく選手と、計量時に余裕があってさらに体重を増やしていく選手とではコンディションが大きく変わってくる。
同じバンタム級での試合を行うと契約した選手間で、こういった差が生まれることは許されない。
ネリの体重超過を受けて、山中の口から「ふざけるな」という言葉が飛び出した。
冷静さを保つことなどできるわけがない。
ここで山中の精神の歯車が狂い始める。
試合本番、精神的にキレてしまった山中はネリに対して突っ込んでいく姿勢を見せた。
前回の試合の反省点をいかすのであれば、序盤は距離をとってネリの連打に気をつけるべきではなかったのか。
ネリのパンチは前回よりもパワーがあった。
動きも良い。
体重超過をしたことにより、明らかにコンディションがプラスの方向へと傾いている。
ネリはドーピング、体重超過、2回ともフェアな試合をしようとしなかった。
いくら勝ったとしても評価などないに等しい。
今後ネリ陣営は世界再挑戦の機会を狙うことになるだろうし、ファイトマネーの良い日本で試合をしたいという願望も持っているだろうが、二度と日本のリングにはあげさせないという処罰を下すべきである。
ネリには厳しい処罰を求めたい。
ネリに必要なのは対戦相手へのリスペクトの気持ちだ。
山中慎介に対してリスペクトの気持ちを持っていれば、ドーピングや体重超過などできるわけがない。
山中はパウンド・フォー・パウンドにもランキングされた実績をもつスーパーチャンピオンである。
世界にも名を知られている。
ネリの愚行により山中のキャリアが傷つけられたことは決して許されるものではない。
ボクシング界全体で、この問題についての議論を交わすべきだと思う。
こんなことが許されるのであれば、伝統あるボクシングのリングが何でもありの場になってしまう。
これは大きな問題である。
ルイス・ネリvs山中慎介
2018・3・1
一夜明けてからも、ネリの体重超過の問題が物議を醸している。
前回の試合、ただでさえドーピング疑惑で世間を騒がせていたのだ。
汚名を挽回するためにも、今回の試合に向けてのコンディション調整はいつも以上に慎重に行うべきであったはず。
これはネリだけの問題ではない。
ネリ陣営全体の問題である。
ボクシングはケンカではない。
試合が終われば、互いに笑顔で健闘をたたえ合う。
これこそがボクシングの素晴らしさなのだ。
試合前日に行われた計量の時点において、両者のコンディションには大きな開きがあった。
極限にまで体重を絞ってきた山中と、肉体に余裕を持ったままのネリ。
ボクシングがなぜ階級制をとっているのか。
それは体重差が(1階級の)1.8キロあるだけでもパワーが別次元のものとなるからだ。
計量時、山中とネリの体重差は2キロ以上あった。
また、極限にまで絞った状態から食事をとり試合までに体重を増やしていく選手と、計量時に余裕があってさらに体重を増やしていく選手とではコンディションが大きく変わってくる。
同じバンタム級での試合を行うと契約した選手間で、こういった差が生まれることは許されない。
ネリの体重超過を受けて、山中の口から「ふざけるな」という言葉が飛び出した。
冷静さを保つことなどできるわけがない。
ここで山中の精神の歯車が狂い始める。
試合本番、精神的にキレてしまった山中はネリに対して突っ込んでいく姿勢を見せた。
前回の試合の反省点をいかすのであれば、序盤は距離をとってネリの連打に気をつけるべきではなかったのか。
ネリのパンチは前回よりもパワーがあった。
動きも良い。
体重超過をしたことにより、明らかにコンディションがプラスの方向へと傾いている。
ネリはドーピング、体重超過、2回ともフェアな試合をしようとしなかった。
いくら勝ったとしても評価などないに等しい。
今後ネリ陣営は世界再挑戦の機会を狙うことになるだろうし、ファイトマネーの良い日本で試合をしたいという願望も持っているだろうが、二度と日本のリングにはあげさせないという処罰を下すべきである。
ネリには厳しい処罰を求めたい。
ネリに必要なのは対戦相手へのリスペクトの気持ちだ。
山中慎介に対してリスペクトの気持ちを持っていれば、ドーピングや体重超過などできるわけがない。
山中はパウンド・フォー・パウンドにもランキングされた実績をもつスーパーチャンピオンである。
世界にも名を知られている。
ネリの愚行により山中のキャリアが傷つけられたことは決して許されるものではない。
ボクシング界全体で、この問題についての議論を交わすべきだと思う。
こんなことが許されるのであれば、伝統あるボクシングのリングが何でもありの場になってしまう。
これは大きな問題である。
WBC世界バンタム級タイトルマッチ
前王者・ルイス・ネリvs元王者・山中慎介
東京・両国国技館 2018・3・1
この試合の前日に衝撃が走った。
公式計量の会場で山中の「ふざけるな」という声が響いたからだ。
ネリが体重計に乗った。
その針は1階級上のスーパーバンタム級を超える55.8キロを指していた。
2.3キロオーバーなど異例中の異例である。
2時間後、再び計量を行ったが54.8キロ。
この時点でネリのタイトルは剥奪された。
ここで疑問が残る。
ネリは2時間で1キロを落としてきた。
1度目の軽量の段階でネリの肉体がカラカラのスポンジ状態であったとするならば、2時間での1キロは難しかったのではないか。
ということはネリの肉体は余裕をもっていた?
ネリの体重超過は確信犯であったのか?
前回の試合、ドーピングの検査で陽性が出た。
ドーピングをしていたのか、していなかったのか。
この真相はネリ本人にしかわからない。
ただ今回の体重超過を受けた時に、前回のドーピングは限りなく「クロ」であると疑わざるを得ない。
山中がどれほどの気持ちを作ってこの試合にかけようとしていたのか…、
これを考えると胸が締めつけられる思いがする。
正々堂々としたフェアな試合に挑ませてあげたかった。
「勝っても負けてもこれが最後」
山中はそう思っていただろう。
国内最高記録保持者である具志堅用高に迫る12度の防衛を果たしてきたスーパーチャンピオンの終焉は、こんな試合で良かったのだろうか。
ネリは最後の試合の相手としてふさわしいのだろうか。
今回のような体重超過という問題は以前からある。
体重超過でタイトルを剥奪されたとしても、勝ち続けていればまたチャンスはやってくるだろうという楽観的な風潮が漂ってしまっている。
「キッチリと減量をして負けるくらいなら、体重超過でも勝った方がマシ」
こんなことを思っている選手もいるのではないか。
今後のボクシング界のことを考えるのであれば、こういったことには断固として厳しい処置を行うべきである。
ルールに乗っ取って厳しい減量をクリアしてきた対戦相手に失礼だとは思わないのか。
世界戦ともなればスポンサーがつき、テレビ中継が入り、会場にもたくさんのファンがつめかける。
世界戦のリングに立つ選手には、これにふさわしいだけの自覚と責任が必要とされるはず。
体重超過などという失態を見せることにより、どれだけの人間の心を傷つけ失望させるのか。
体重超過をした選手は永久追放でも構わない。
2度と世界戦のリングに上がるべきではないのだ。
この試合後、ネリは勝利の雄たけびをあげていた。
ネリ陣営が喜びを爆発させる姿を冷めた目で見ていた人は多いはず。
いや、会場にいた全員がネリに対して疑問を感じていたのではないか。
ルール違反をした人間が、なぜここまで喜べるのか。
山中に、帝拳陣営に、そして会場のお客さんに詫びなくてはならないのではないのか。
後味が悪い。
試合内容に触れる。
山中のボクサー人生はモレノとの2戦目で終わっていたのだと思う。
世界戦をこなしていく中で徐々に打たれ弱くなっていった。
ダウン癖がついてしまい、何でもないパンチでもグラついてしまう場面が増えた。
今回の試合は、山中のダウン癖がどこまで修正されているかにかかっていた。
世界戦のリングにおいて、1発ももらわないということは不可能に近い。
山中が優勢に試合を運んでいたとしても、1発でグラついてしまえば形勢は逆転してしまう。
1ラウンド、
ネリのパンチがカウンターで入った瞬間に試合は終わった。
山中のすべてが終わってしまったからだ。
世界戦のリングに上がる選手が、こんなパンチ1発でグラつくなどということはない。
山中は、もう世界戦のリングに上がれる状態ではなかった。
これなら日本チャンピオンクラスの選手と試合をしたってどうなるかわからない。
約20年前の1999年、同じWBCバンタム級のタイトルをかけて行われた試合を思い出していた。
ウィラポンvs辰吉丈一郎。
前年、辰吉は壮絶なるKO負けを喫していた。
すべてをかけて挑んだリマッチ。
辰吉の肉体に蓄積されたダメージが抜けきることはなかった。
人間サンドバックとなった辰吉の姿。
今回の山中が、あの時の辰吉の姿と重なって見えた。
かつてのスーパーチャンピオンの面影はもうない。
山中には「お疲れ様」と言いたい。
山中は日本ボクシング界の歴史に残るスーパーチャンピオンであることに間違いはない。
伝説を作り上げてきた神の左は永遠に語り継がれるであろう。
前王者・ルイス・ネリvs元王者・山中慎介
東京・両国国技館 2018・3・1
この試合の前日に衝撃が走った。
公式計量の会場で山中の「ふざけるな」という声が響いたからだ。
ネリが体重計に乗った。
その針は1階級上のスーパーバンタム級を超える55.8キロを指していた。
2.3キロオーバーなど異例中の異例である。
2時間後、再び計量を行ったが54.8キロ。
この時点でネリのタイトルは剥奪された。
ここで疑問が残る。
ネリは2時間で1キロを落としてきた。
1度目の軽量の段階でネリの肉体がカラカラのスポンジ状態であったとするならば、2時間での1キロは難しかったのではないか。
ということはネリの肉体は余裕をもっていた?
ネリの体重超過は確信犯であったのか?
前回の試合、ドーピングの検査で陽性が出た。
ドーピングをしていたのか、していなかったのか。
この真相はネリ本人にしかわからない。
ただ今回の体重超過を受けた時に、前回のドーピングは限りなく「クロ」であると疑わざるを得ない。
山中がどれほどの気持ちを作ってこの試合にかけようとしていたのか…、
これを考えると胸が締めつけられる思いがする。
正々堂々としたフェアな試合に挑ませてあげたかった。
「勝っても負けてもこれが最後」
山中はそう思っていただろう。
国内最高記録保持者である具志堅用高に迫る12度の防衛を果たしてきたスーパーチャンピオンの終焉は、こんな試合で良かったのだろうか。
ネリは最後の試合の相手としてふさわしいのだろうか。
今回のような体重超過という問題は以前からある。
体重超過でタイトルを剥奪されたとしても、勝ち続けていればまたチャンスはやってくるだろうという楽観的な風潮が漂ってしまっている。
「キッチリと減量をして負けるくらいなら、体重超過でも勝った方がマシ」
こんなことを思っている選手もいるのではないか。
今後のボクシング界のことを考えるのであれば、こういったことには断固として厳しい処置を行うべきである。
ルールに乗っ取って厳しい減量をクリアしてきた対戦相手に失礼だとは思わないのか。
世界戦ともなればスポンサーがつき、テレビ中継が入り、会場にもたくさんのファンがつめかける。
世界戦のリングに立つ選手には、これにふさわしいだけの自覚と責任が必要とされるはず。
体重超過などという失態を見せることにより、どれだけの人間の心を傷つけ失望させるのか。
体重超過をした選手は永久追放でも構わない。
2度と世界戦のリングに上がるべきではないのだ。
この試合後、ネリは勝利の雄たけびをあげていた。
ネリ陣営が喜びを爆発させる姿を冷めた目で見ていた人は多いはず。
いや、会場にいた全員がネリに対して疑問を感じていたのではないか。
ルール違反をした人間が、なぜここまで喜べるのか。
山中に、帝拳陣営に、そして会場のお客さんに詫びなくてはならないのではないのか。
後味が悪い。
試合内容に触れる。
山中のボクサー人生はモレノとの2戦目で終わっていたのだと思う。
世界戦をこなしていく中で徐々に打たれ弱くなっていった。
ダウン癖がついてしまい、何でもないパンチでもグラついてしまう場面が増えた。
今回の試合は、山中のダウン癖がどこまで修正されているかにかかっていた。
世界戦のリングにおいて、1発ももらわないということは不可能に近い。
山中が優勢に試合を運んでいたとしても、1発でグラついてしまえば形勢は逆転してしまう。
1ラウンド、
ネリのパンチがカウンターで入った瞬間に試合は終わった。
山中のすべてが終わってしまったからだ。
世界戦のリングに上がる選手が、こんなパンチ1発でグラつくなどということはない。
山中は、もう世界戦のリングに上がれる状態ではなかった。
これなら日本チャンピオンクラスの選手と試合をしたってどうなるかわからない。
約20年前の1999年、同じWBCバンタム級のタイトルをかけて行われた試合を思い出していた。
ウィラポンvs辰吉丈一郎。
前年、辰吉は壮絶なるKO負けを喫していた。
すべてをかけて挑んだリマッチ。
辰吉の肉体に蓄積されたダメージが抜けきることはなかった。
人間サンドバックとなった辰吉の姿。
今回の山中が、あの時の辰吉の姿と重なって見えた。
かつてのスーパーチャンピオンの面影はもうない。
山中には「お疲れ様」と言いたい。
山中は日本ボクシング界の歴史に残るスーパーチャンピオンであることに間違いはない。
伝説を作り上げてきた神の左は永遠に語り継がれるであろう。
WBA世界ミドル級タイトルマッチ
正規王者・アッサン・エンダムvs挑戦者・村田諒太
2017.10.22 東京・両国国技館
この試合、リアルタイムで見ていた。
どこか違和感を覚えていた。
エンダムの身体に力が入っていない。
試合後、ある情報が流れた。
「エンダムの体調が最悪であった」
ニュースから転載する。
『9月に左足首を負傷。直後にキャンプのため米マイアミに入ったが、今度は40度近い発熱に苦しみ、おまけに大型ハリケーンの影響でジムも使えなかったという。「キャンセルも考えたが、トリプル世界戦でもあったので」とこぼした。』
世界戦のリングにおいてダウンも喫していない状態での棄権は稀なことである。
『エンダムは8回を前に棄権した。「無駄にパンチを受けない決断をした」。5回あたりから体調に異変を感じた。セコンドに「もらうはずのない左ジャブをもらう。いつもの状態ではない」と棄権を勧められたという。』
序盤からエンダムは村田を過剰に恐れているように見えた。
前回の試合で「村田の右」の威力は身をもって感じている。
ダウンも奪われた。
村田のベストパンチをもらってはいけない。
今回の試合の重要なテーマであったと思う。
村田は中間距離よりも若干遠い位置を得意とする。
村田はこの位置から伸びるように放たれる右ストレートを合わせていく。
エンダムが注意していたのは距離である。
アウトボクシングで距離をとるか、
一気に間合いを縮めて距離を詰めるか。
至近距離ではクリンチを多用した。
なぜ?
疑問を感じる。
村田の強烈なパンチを受けているのであればクリンチをしても構わない。
しかし、まだ村田が手を出す前からクリンチを始めていたのだ。
前回の試合、
村田はエンダムを実像以上の存在として受け止めていた。
「エンダムはダウンを喫しても回復が早い」
村田はこの幻影に怯えていた。
ダウンを奪っても、
勝機があっても、
エンダムに対して踏み込んでいかない。
「エンダムは回復が早い」
目の前にいるエンダムの姿よりも、
事前にリサーチをかけていた情報を重視した。
これにより、
村田は不自然なほどに消極的なボクシングを展開することになる。
今回の試合、
これが逆転していた。
エンダムが村田を実情以上の存在として見ていたのではないか。
村田が何もしていない段階でエンダムは過剰に守りに入っている。
前回のように、
中間距離で手数を出せば良かったのに。
村田はどこか臆病なところがある。
前回の試合、
向かい合ったのは「ミドル級の世界王者」。
いよいよミドル級の世界最高峰の相手と試合をする。
自分が世界最高の男に通用するのか?
自分への疑念。
自信を持って試合に挑むということができない。
ガードをして、
相手の出方を見て、
パンチの軌道を読んで、
試合中でありながらもエンダムをリサーチしている。
これは本番の試合なのだ。
リサーチしている場合ではない。
もっと攻め込め!
村田のボクシングは消極的に映っていた。
微妙な判定。
エンダムに僅差で敗れた。
世間からは「村田が勝っていた」との声が爆発。
WBAでも大問題となり、
異例ともいえるダイレクトリマッチが組まれた。
村田は感じとった。
「自分のボクシングはミドル級の世界最高峰でも通用する」
序盤から村田は自身にGOサインを出していた。
やる時はやる。
ダイレクトでの右を放つ。
1発、2発、倒すという気迫が伝わってくる。
エンダムを気持ちで押している。
村田は試合中にも関わらず笑顔を見せていた。
「村田はこの試合を楽しんでいる」
エンダムからすれば脅威に感じたことだろう。
エンダムが至近距離をとってくることは村田陣営でも予測していた。
今回、練習してきたのは至近距離での攻撃。
ショートでのフック、アッパー、そしてストレート。
村田の狙いが的中。
ショートでのパンチでエンダムを圧倒する。
これに怯んだエンダムはバックステップで距離をとる。
エンダムの戦術がまとまらない。
至近距離での戦いに引きずり込み、
自身のパンチを当ててすぐにクリンチで逃げるのか。
アウトボクシングを展開して、
入っては出て、入っては出てを繰り返すのか。
エンダムの動揺。
途中からエンダムの身体に力が入っていないことが明白になっていく。
エンダムはディフェンス能力の高い選手である。
いくら村田が練習してきたとはいえ、
村田のパンチを被弾する回数が多すぎる。
村田は自信を持っている「右のパンチ」に比べて、
「左のパンチ」が極端に弱い。
通常は左を多用して右を当てていくのだが、
村田は本能でも「左では倒せない」とわかっているのだろう。
ダイレクトでの右というパターンが多い。
エンダムのディフェンス能力があれば、
ダイレクトでの右をここまで被弾するはずがない。
ボクサーからすれば、
ダイレクトでの右を当てさせてもらえるのであればこんなにありがたい話はない。
ただ、思いっきり「ぶん殴ればいい」のだから。
しかし、ボクシングは「パンチングマシーン」をぶん殴るのとは違う。
相手は人間であり、的を絞らせないよう不可測に動いてくる。
だからこそ、まずは左を多用していく必要があるのだ。
村田は「相手を倒す」=「右でぶん殴る」と考えている。
プロ転向後の試合も、
ずっとダイレクトでの右に頼ってきた。
この右が当たらずにやきもきしてきた。
村田が進化するには、
いかに左を有効に使えるかがテーマであったはず。
今回、
エンダムが不調であったがゆえに村田の左が当たっていく。
左ジャブ、
左でのボディ、
左が当たるから自然と次につながる右が出る。
左から右、左左と続けてからの右、
村田のボクシングにスムーズなコンビネーションが生まれ始めていた。
村田のボクシングが進化していく。
アマチュア色の強いボクシングスタイルから、
プロボクシングの世界においての「自分のスタイル」を見出したのか。
前回の試合、
村田は試合をしている「当事者」であったはずなのに、
どこか「傍観者」の位置にいたような気がする。
試合の最後まで傍観者であり続けた。
判定の結果を聞いた時も、
他人事としてその事実を見つめていた印象がある。
今回の試合、
村田は当事者であった。
エンダムを客観的に見るのではなく、
目の前で試合をする対戦相手として見ていた。
TKOでの勝利が決まった時、
村田の顔が一気に崩れた。
前回の試合、
あの判定が発表される場面において、
「勝者・村田諒太」とコールをされてもこんな表情を見せることはなかっただろう。
自分が行う試合を、
傍観者として見ているのか、
当事者として見ているのか。
ここには大きな違いがあって当然である。
今回、
いろんな意味で「熱い」村田を見ることができたような気がする。
気持ちを前面に出して戦ったこと。
必死にパンチを出していったこと。
試合後にはプレッシャーから解放された柔らかい表情を見せたこと。
村田から人間臭さを感じた。
多くの人間が望んでいたことはこれではなかっただろうか。
スポーツの世界でも、
やはり人間は人間が見たいのだ。
血の通った人間が生み出す人間ドラマ。
ここに感動するのだから。
これから、
村田には更なる強敵との戦いが待ち受けている。
期待と不安。
しかし、今は勝利の余韻に浸っていたい。
エンダムの不調も含めて、
この日の夜は村田諒大のためにあったのだ。
勝利の女神は村田に微笑んだ。
正規王者・アッサン・エンダムvs挑戦者・村田諒太
2017.10.22 東京・両国国技館
この試合、リアルタイムで見ていた。
どこか違和感を覚えていた。
エンダムの身体に力が入っていない。
試合後、ある情報が流れた。
「エンダムの体調が最悪であった」
ニュースから転載する。
『9月に左足首を負傷。直後にキャンプのため米マイアミに入ったが、今度は40度近い発熱に苦しみ、おまけに大型ハリケーンの影響でジムも使えなかったという。「キャンセルも考えたが、トリプル世界戦でもあったので」とこぼした。』
世界戦のリングにおいてダウンも喫していない状態での棄権は稀なことである。
『エンダムは8回を前に棄権した。「無駄にパンチを受けない決断をした」。5回あたりから体調に異変を感じた。セコンドに「もらうはずのない左ジャブをもらう。いつもの状態ではない」と棄権を勧められたという。』
序盤からエンダムは村田を過剰に恐れているように見えた。
前回の試合で「村田の右」の威力は身をもって感じている。
ダウンも奪われた。
村田のベストパンチをもらってはいけない。
今回の試合の重要なテーマであったと思う。
村田は中間距離よりも若干遠い位置を得意とする。
村田はこの位置から伸びるように放たれる右ストレートを合わせていく。
エンダムが注意していたのは距離である。
アウトボクシングで距離をとるか、
一気に間合いを縮めて距離を詰めるか。
至近距離ではクリンチを多用した。
なぜ?
疑問を感じる。
村田の強烈なパンチを受けているのであればクリンチをしても構わない。
しかし、まだ村田が手を出す前からクリンチを始めていたのだ。
前回の試合、
村田はエンダムを実像以上の存在として受け止めていた。
「エンダムはダウンを喫しても回復が早い」
村田はこの幻影に怯えていた。
ダウンを奪っても、
勝機があっても、
エンダムに対して踏み込んでいかない。
「エンダムは回復が早い」
目の前にいるエンダムの姿よりも、
事前にリサーチをかけていた情報を重視した。
これにより、
村田は不自然なほどに消極的なボクシングを展開することになる。
今回の試合、
これが逆転していた。
エンダムが村田を実情以上の存在として見ていたのではないか。
村田が何もしていない段階でエンダムは過剰に守りに入っている。
前回のように、
中間距離で手数を出せば良かったのに。
村田はどこか臆病なところがある。
前回の試合、
向かい合ったのは「ミドル級の世界王者」。
いよいよミドル級の世界最高峰の相手と試合をする。
自分が世界最高の男に通用するのか?
自分への疑念。
自信を持って試合に挑むということができない。
ガードをして、
相手の出方を見て、
パンチの軌道を読んで、
試合中でありながらもエンダムをリサーチしている。
これは本番の試合なのだ。
リサーチしている場合ではない。
もっと攻め込め!
村田のボクシングは消極的に映っていた。
微妙な判定。
エンダムに僅差で敗れた。
世間からは「村田が勝っていた」との声が爆発。
WBAでも大問題となり、
異例ともいえるダイレクトリマッチが組まれた。
村田は感じとった。
「自分のボクシングはミドル級の世界最高峰でも通用する」
序盤から村田は自身にGOサインを出していた。
やる時はやる。
ダイレクトでの右を放つ。
1発、2発、倒すという気迫が伝わってくる。
エンダムを気持ちで押している。
村田は試合中にも関わらず笑顔を見せていた。
「村田はこの試合を楽しんでいる」
エンダムからすれば脅威に感じたことだろう。
エンダムが至近距離をとってくることは村田陣営でも予測していた。
今回、練習してきたのは至近距離での攻撃。
ショートでのフック、アッパー、そしてストレート。
村田の狙いが的中。
ショートでのパンチでエンダムを圧倒する。
これに怯んだエンダムはバックステップで距離をとる。
エンダムの戦術がまとまらない。
至近距離での戦いに引きずり込み、
自身のパンチを当ててすぐにクリンチで逃げるのか。
アウトボクシングを展開して、
入っては出て、入っては出てを繰り返すのか。
エンダムの動揺。
途中からエンダムの身体に力が入っていないことが明白になっていく。
エンダムはディフェンス能力の高い選手である。
いくら村田が練習してきたとはいえ、
村田のパンチを被弾する回数が多すぎる。
村田は自信を持っている「右のパンチ」に比べて、
「左のパンチ」が極端に弱い。
通常は左を多用して右を当てていくのだが、
村田は本能でも「左では倒せない」とわかっているのだろう。
ダイレクトでの右というパターンが多い。
エンダムのディフェンス能力があれば、
ダイレクトでの右をここまで被弾するはずがない。
ボクサーからすれば、
ダイレクトでの右を当てさせてもらえるのであればこんなにありがたい話はない。
ただ、思いっきり「ぶん殴ればいい」のだから。
しかし、ボクシングは「パンチングマシーン」をぶん殴るのとは違う。
相手は人間であり、的を絞らせないよう不可測に動いてくる。
だからこそ、まずは左を多用していく必要があるのだ。
村田は「相手を倒す」=「右でぶん殴る」と考えている。
プロ転向後の試合も、
ずっとダイレクトでの右に頼ってきた。
この右が当たらずにやきもきしてきた。
村田が進化するには、
いかに左を有効に使えるかがテーマであったはず。
今回、
エンダムが不調であったがゆえに村田の左が当たっていく。
左ジャブ、
左でのボディ、
左が当たるから自然と次につながる右が出る。
左から右、左左と続けてからの右、
村田のボクシングにスムーズなコンビネーションが生まれ始めていた。
村田のボクシングが進化していく。
アマチュア色の強いボクシングスタイルから、
プロボクシングの世界においての「自分のスタイル」を見出したのか。
前回の試合、
村田は試合をしている「当事者」であったはずなのに、
どこか「傍観者」の位置にいたような気がする。
試合の最後まで傍観者であり続けた。
判定の結果を聞いた時も、
他人事としてその事実を見つめていた印象がある。
今回の試合、
村田は当事者であった。
エンダムを客観的に見るのではなく、
目の前で試合をする対戦相手として見ていた。
TKOでの勝利が決まった時、
村田の顔が一気に崩れた。
前回の試合、
あの判定が発表される場面において、
「勝者・村田諒太」とコールをされてもこんな表情を見せることはなかっただろう。
自分が行う試合を、
傍観者として見ているのか、
当事者として見ているのか。
ここには大きな違いがあって当然である。
今回、
いろんな意味で「熱い」村田を見ることができたような気がする。
気持ちを前面に出して戦ったこと。
必死にパンチを出していったこと。
試合後にはプレッシャーから解放された柔らかい表情を見せたこと。
村田から人間臭さを感じた。
多くの人間が望んでいたことはこれではなかっただろうか。
スポーツの世界でも、
やはり人間は人間が見たいのだ。
血の通った人間が生み出す人間ドラマ。
ここに感動するのだから。
これから、
村田には更なる強敵との戦いが待ち受けている。
期待と不安。
しかし、今は勝利の余韻に浸っていたい。
エンダムの不調も含めて、
この日の夜は村田諒大のためにあったのだ。
勝利の女神は村田に微笑んだ。
2017年9月9日(日本時間10日)、
日本ボクシング界にとっての新しい扉が開いた。
かつて海外での世界タイトルマッチを実現
させ、そこで名を馳せることに成功した日本人ボクサーがいる。
西岡利晃、三浦隆司、亀海喜寛、
彼らは海外での実績を積んだうえでアメリカでの世界タイトルマッチを実現させたのだ。
井上尚弥。
初の海外がいきなりアメリカ。
しかも軽量級最強を決める「スーパーフライ」と銘打たれた大きな興行のセミファイナル。
海外で実績のない日本人ボクサーにアメリカからのオファーが届いたのだ。
ファイトマネーもロマゴンに続く2番目の高額が用意されていた。
破格の待遇。
世界は今、軽量級のスターを必要としている。
防衛戦の相手となったのはニエベス。
井上の相手としては物足りないと言わざるを得ない。
予想通り、試合は一方的なものになった。
井上が圧倒した。
試合後、井上はこうコメントしている。
「試合は相手があってのこと。今日みたいな一方的な、相手の選手に勝つ気がないような試合だと試合自体が枯れちゃうので。白熱した試合がしたいです」
ニエベスにだって勝つ気はあっただろう。
しかし、井上の圧力の前に何もできなかったのだ。
勝つことよりも倒れないことを選んだ。
6回終了時にニエベス陣営が試合を棄権。
井上がイメージしていたダウンを奪っての勝利…とはならなかった。
井上は圧倒的な強さを見せつけることができた。
ここで1つの疑念。
相手がもっと強い人間であればどうなるのか…?
アメリカは井上の次戦として実力のある相手を求めるだろう。
今回のようなただの防衛戦では満足ができない。
この日のメインイベント。
世界のボクシング界の1つの幕が降ろされた。
パウンド・フォー・パウンドにおいて1位に君臨していた男。
軽量級でありながら世界最強であると言わしめていた男が、壮絶なるKO負けを喫したのだ。
同じ相手に2連敗。
前回は微妙な判定であり、「判定がおかしい」という物議を醸す結果となったが今回は言い訳ができない。
最強の男がリング上で大の字になったのだから。
ロマゴンはスーパーフライ級の選手ではない。
フライ級までのロマゴンが、この階級では見せられない。
技術以前の問題で、明らかに身体そのものの力で劣勢に立たされていた。
フライ級の選手がウェイトだけをスーパーフライ級に上げただけ。
そんな印象である。
ロマゴンvs井上尚弥。
世紀の一戦は泡となって消えた。
しかし、見方を変えれば井上にさらなる期待と注目が集まるということだ。
ロマゴンが座っていた座席に、ここから井上が座ることができる。
早くも井上の次戦が騒がれている。
ロマゴンを2度にわたって破ったWBC同級王者・シーサケット・ソールンビサイとの王座統一戦。
これはアメリカでも話題となるだろう。
そして、ここに待ったをかける男が現れた。
IBF同級王者・ジェルウィン・アンカハスである。
「我々はその戦いに準備ができている」
井上は次戦を年末に…というイメージを持っているだろう。
進化している肉体がスーパーフライ級にとどまっていられる時間はもう長くない。
ロマゴン戦がなくなった今、いつまでスーパーフライ級でやるのか。
スーパーフライ級でやり残したこと。
この階級で最強であることの証明。
それには他団体王者との統一戦しかない。
実現をする上で最も近い存在は、やはりIBF王者のアンカハスであろう。
長谷川穂積、内山高志、山中慎介、……、
日本にはありえないほどに強い世界王者がいた。
その階級において世界最強であると思われた男たちには、その全盛期にアメリカのリングでそれを証明してほしかった。
ついに日本人世界王者がアメリカへの扉を開ける。
井上尚弥の今後が楽しみである。
日本ボクシング界にとっての新しい扉が開いた。
かつて海外での世界タイトルマッチを実現
させ、そこで名を馳せることに成功した日本人ボクサーがいる。
西岡利晃、三浦隆司、亀海喜寛、
彼らは海外での実績を積んだうえでアメリカでの世界タイトルマッチを実現させたのだ。
井上尚弥。
初の海外がいきなりアメリカ。
しかも軽量級最強を決める「スーパーフライ」と銘打たれた大きな興行のセミファイナル。
海外で実績のない日本人ボクサーにアメリカからのオファーが届いたのだ。
ファイトマネーもロマゴンに続く2番目の高額が用意されていた。
破格の待遇。
世界は今、軽量級のスターを必要としている。
防衛戦の相手となったのはニエベス。
井上の相手としては物足りないと言わざるを得ない。
予想通り、試合は一方的なものになった。
井上が圧倒した。
試合後、井上はこうコメントしている。
「試合は相手があってのこと。今日みたいな一方的な、相手の選手に勝つ気がないような試合だと試合自体が枯れちゃうので。白熱した試合がしたいです」
ニエベスにだって勝つ気はあっただろう。
しかし、井上の圧力の前に何もできなかったのだ。
勝つことよりも倒れないことを選んだ。
6回終了時にニエベス陣営が試合を棄権。
井上がイメージしていたダウンを奪っての勝利…とはならなかった。
井上は圧倒的な強さを見せつけることができた。
ここで1つの疑念。
相手がもっと強い人間であればどうなるのか…?
アメリカは井上の次戦として実力のある相手を求めるだろう。
今回のようなただの防衛戦では満足ができない。
この日のメインイベント。
世界のボクシング界の1つの幕が降ろされた。
パウンド・フォー・パウンドにおいて1位に君臨していた男。
軽量級でありながら世界最強であると言わしめていた男が、壮絶なるKO負けを喫したのだ。
同じ相手に2連敗。
前回は微妙な判定であり、「判定がおかしい」という物議を醸す結果となったが今回は言い訳ができない。
最強の男がリング上で大の字になったのだから。
ロマゴンはスーパーフライ級の選手ではない。
フライ級までのロマゴンが、この階級では見せられない。
技術以前の問題で、明らかに身体そのものの力で劣勢に立たされていた。
フライ級の選手がウェイトだけをスーパーフライ級に上げただけ。
そんな印象である。
ロマゴンvs井上尚弥。
世紀の一戦は泡となって消えた。
しかし、見方を変えれば井上にさらなる期待と注目が集まるということだ。
ロマゴンが座っていた座席に、ここから井上が座ることができる。
早くも井上の次戦が騒がれている。
ロマゴンを2度にわたって破ったWBC同級王者・シーサケット・ソールンビサイとの王座統一戦。
これはアメリカでも話題となるだろう。
そして、ここに待ったをかける男が現れた。
IBF同級王者・ジェルウィン・アンカハスである。
「我々はその戦いに準備ができている」
井上は次戦を年末に…というイメージを持っているだろう。
進化している肉体がスーパーフライ級にとどまっていられる時間はもう長くない。
ロマゴン戦がなくなった今、いつまでスーパーフライ級でやるのか。
スーパーフライ級でやり残したこと。
この階級で最強であることの証明。
それには他団体王者との統一戦しかない。
実現をする上で最も近い存在は、やはりIBF王者のアンカハスであろう。
長谷川穂積、内山高志、山中慎介、……、
日本にはありえないほどに強い世界王者がいた。
その階級において世界最強であると思われた男たちには、その全盛期にアメリカのリングでそれを証明してほしかった。
ついに日本人世界王者がアメリカへの扉を開ける。
井上尚弥の今後が楽しみである。
IBF世界スーパーバンタム級タイトルマッチ
王者・小國以載vs挑戦者・岩佐亮佑
2017.9.13 エディオンアリーナ大阪
試合後、小國は引退を発表した。
「完敗。やっぱり強かった。(自分は)サウスポーにめっぽう弱い。百発百中でもらっていた。1回から4回に全力でいくという作戦だった。(今後は)引退です。すっきりしてます。最後が岩佐でよかった」
昨年の大晦日、とんでもない光景を目の当たりにした。
22戦22勝全KO。
ありえないレコードをもつ怪物がいた。
この階級、このベルトはジョナサン・グスマンのものであった。
小國は怪物に挑んだ。
目を疑う光景がそこにはあった。
グスマンをボディでダウンさせた。
グスマンに対してまったくビビらない。
ガンガンとインファイトを仕掛けていく。
最終的には当たり前のような顔をしてグスマンを破ったのだ。
「小國、凄すぎる…」
この時のグスマンを破ったことは、日本ボクシング界の歴史に残るような快挙であると思っている。
タイトルを獲ったのは度胸。
そして、この試合を落としたのもやはり度胸であったのではないか。
小國は序盤から勝負をかけるつもりでいた。
それはいい。
しかし、サウスポーの岩佐に対してなぜ右へ右へと入っていくのか。
岩佐の左ストレートは強い。
岩佐は、小國の左ジャブの打ち終わりに合わせて左ストレートを放っていた。
岩佐の強い左がとんでくる。
それでも小國はビビらない。
あくまでも右へ右へと入っていく。
確かに右に入らなければ自分のパンチは当たらない。
グスマンからダウンを奪ったボディを放つためには右へと入る必要がある。
しかし、あまりにも不用意すぎたのではないか。
岩佐の左ストレートを封じるために何かをしたのか?
左ストレートをかわすために何かをしたのか?
岩佐の得意な展開へと、ただ付き合っていってしまったような印象を受ける。
1ラウンド、ダウンを喫する。
2ラウンドは2度のダウン。
もう勝負は見えているのではないか。
しかし、3ラウンドからまたガンガンと前に出る。
グスマンを破った男はやはり象の心臓を持っている。
それはわかるのだが、その勇敢さで前に出ることでしか戦うことができないのだろうか。
良い意味での「臆病さ」がほしい。
岩佐のパンチをもらわないために、どうするべきなのか?
この対策を立てていたらどうなっていただろう。
対サウスポーのセオリー通りに、左に左に入っていったらどうなっていたのだろう。
私はもっと小國の試合が見たかった。
サウスポーが苦手であれば、
もう1試合でも2試合でもいいから、
ボクサータイプの相手との試合が見たかった。
小國には「何かやってくれるのではないか…」という期待感を持ってしまう。
この試合でも同じ。
ダウンを喫しても、それが劇的なドラマを生み出すための前フリではないか…と期待してしまう自分がいた。
小國の敗戦。
小國の引退。
残念でならない。
グスマンに対して堂々と向かっていったあの姿は一生忘れることはないだろう。
王者・小國以載vs挑戦者・岩佐亮佑
2017.9.13 エディオンアリーナ大阪
試合後、小國は引退を発表した。
「完敗。やっぱり強かった。(自分は)サウスポーにめっぽう弱い。百発百中でもらっていた。1回から4回に全力でいくという作戦だった。(今後は)引退です。すっきりしてます。最後が岩佐でよかった」
昨年の大晦日、とんでもない光景を目の当たりにした。
22戦22勝全KO。
ありえないレコードをもつ怪物がいた。
この階級、このベルトはジョナサン・グスマンのものであった。
小國は怪物に挑んだ。
目を疑う光景がそこにはあった。
グスマンをボディでダウンさせた。
グスマンに対してまったくビビらない。
ガンガンとインファイトを仕掛けていく。
最終的には当たり前のような顔をしてグスマンを破ったのだ。
「小國、凄すぎる…」
この時のグスマンを破ったことは、日本ボクシング界の歴史に残るような快挙であると思っている。
タイトルを獲ったのは度胸。
そして、この試合を落としたのもやはり度胸であったのではないか。
小國は序盤から勝負をかけるつもりでいた。
それはいい。
しかし、サウスポーの岩佐に対してなぜ右へ右へと入っていくのか。
岩佐の左ストレートは強い。
岩佐は、小國の左ジャブの打ち終わりに合わせて左ストレートを放っていた。
岩佐の強い左がとんでくる。
それでも小國はビビらない。
あくまでも右へ右へと入っていく。
確かに右に入らなければ自分のパンチは当たらない。
グスマンからダウンを奪ったボディを放つためには右へと入る必要がある。
しかし、あまりにも不用意すぎたのではないか。
岩佐の左ストレートを封じるために何かをしたのか?
左ストレートをかわすために何かをしたのか?
岩佐の得意な展開へと、ただ付き合っていってしまったような印象を受ける。
1ラウンド、ダウンを喫する。
2ラウンドは2度のダウン。
もう勝負は見えているのではないか。
しかし、3ラウンドからまたガンガンと前に出る。
グスマンを破った男はやはり象の心臓を持っている。
それはわかるのだが、その勇敢さで前に出ることでしか戦うことができないのだろうか。
良い意味での「臆病さ」がほしい。
岩佐のパンチをもらわないために、どうするべきなのか?
この対策を立てていたらどうなっていただろう。
対サウスポーのセオリー通りに、左に左に入っていったらどうなっていたのだろう。
私はもっと小國の試合が見たかった。
サウスポーが苦手であれば、
もう1試合でも2試合でもいいから、
ボクサータイプの相手との試合が見たかった。
小國には「何かやってくれるのではないか…」という期待感を持ってしまう。
この試合でも同じ。
ダウンを喫しても、それが劇的なドラマを生み出すための前フリではないか…と期待してしまう自分がいた。
小國の敗戦。
小國の引退。
残念でならない。
グスマンに対して堂々と向かっていったあの姿は一生忘れることはないだろう。
WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ
王者・田中恒成vs挑戦者・パランポン・CPフレッシュマート
2017.9.13 エディオンアリーナ大阪
日本ボクシング界屈指の天才は、ライトフライ級における究極のボクサーへと変貌を遂げていた。
完璧なるボクサー。
4団体の王者の中で、ライトフライ級のトップは田中恒成である。
ライトフライ級のタイトルを奪取した試合、
初防衛戦、
ともにそう確信させるほどの圧倒的な内容を見せつけてきた。
今回はWBOランキング13位のパランポンが相手である。
結果はわかっている。
田中が序盤から圧倒するだろう。
そう思っていた。
しかし…。
目を疑った。
1ラウンド、田中がダウンを喫したのである。
パンチをモロに喰らう場面が見られた。
ラウンドを重ねるごとに顔面が腫れていく。
偶然のバッティングにより瞼から流血。
思わぬ苦戦を強いられている。
こういった事態になったのは、「パランポンが意外と強かった」ということに尽きる。
田中としては序盤からガンガンと圧力をかけ、早いランドで仕留めようという作戦だったと思う。
しかし、パランポンの思わぬ反撃にあいダウンを喫した。
2ラウンド、3ラウンドあたりから田中が作戦を変えていく。
本来の器用さを見せ始める。
左ジャブから、左アッパー、左だけでも多彩なるバリエーションのパンチを繰り出す。
序盤には見せなかった変幻自在のフットワーク。
パランポンは「でんでん太鼓」である。
軸がぶれずに、その軸を中心としてコンパクトなフック、ストレートを素早い回転によって繰り出している。
パランポンのパンチの出し方を見て私は感心していた。
では、パランポンを攻略するためにはどうすればいいのか?
でんでん太鼓はターゲットが定まり、それに向かって軸が定まった時に威力を発揮する。
となればターゲットを定めさせなければいい。
序盤、田中は仕留めるためにと至近距離、しかも同じポジションに立ち続けていた。
だからパランポンのパンチを浴びることになった。
田中に必要だったのは左右の動きである。
同じ位置に固定せず、左右にステップワークで身体を動かす。
こうなればパランポンは的を絞れなくなりパンチを出すことさえ難しくなってしまう。
田中は中盤に差しかかるあたりでこれに気づいた。
縦の動きよりも横の動き。
横の動きの中で繰り出す多彩なるパンチの打ち分け。
田中が試合の流れを自分のもとへと引き寄せていく。
8ラウンド、田中は手をとめ、パランポンの攻撃をフットワークでかわし続けた。
パランポンの攻撃のパターン、パンチの軌道、これらをしっかりと読むことができたようだ。
9ラウンド、衝撃が走る。
パランポンが倒れた。
立ち上がった時には、すでに身体に力が入っていない。
田中が一気に出る。
多彩なコンビネーションでラッシュ。
レフェリーが試合をとめた。
9ラウンド、TKOでの勝利。
田中が予想外に苦戦した。
緊迫した試合内容。
エンターテイメントとして見る分にはおもしろい試合であったように思う。
リングサイドにはWBA王者・田口がいた。
田中としては、田口にプレッシャーをかけるためにも「圧勝」して防衛したかったことだろう。
世界王者が乱立するボクシング界。
ただの王者でいたのでは評価されない。
誰とやるのか、どういう試合をするのか。
内容が問われるのだ。
日本人対決。
TBSの中継では過去に行われた3試合の映像が流れた。
薬師寺vs辰吉、畑山vs坂本、井岡vs八重樫、
どれも壮絶なる打ち合いであった。
人々の記憶に残り続ける名勝負であったと言えるだろう。
井岡vs八重樫に続く、日本人同士による団体統一戦の実現はなるのか。
試合後、田中は頭痛を訴え、大事をとって病院に向かったそうだ。
国内最短記録で世界王者、2階級制覇、天才が味わった思わぬ苦戦。
喫したダウン、腫れ上がった瞼、そして流血。
この悔しさが、天才をさらに覚醒させていくことになるだろう。
田中vs田口、ぜひ実現させてほしい。
楽しみである。
王者・田中恒成vs挑戦者・パランポン・CPフレッシュマート
2017.9.13 エディオンアリーナ大阪
日本ボクシング界屈指の天才は、ライトフライ級における究極のボクサーへと変貌を遂げていた。
完璧なるボクサー。
4団体の王者の中で、ライトフライ級のトップは田中恒成である。
ライトフライ級のタイトルを奪取した試合、
初防衛戦、
ともにそう確信させるほどの圧倒的な内容を見せつけてきた。
今回はWBOランキング13位のパランポンが相手である。
結果はわかっている。
田中が序盤から圧倒するだろう。
そう思っていた。
しかし…。
目を疑った。
1ラウンド、田中がダウンを喫したのである。
パンチをモロに喰らう場面が見られた。
ラウンドを重ねるごとに顔面が腫れていく。
偶然のバッティングにより瞼から流血。
思わぬ苦戦を強いられている。
こういった事態になったのは、「パランポンが意外と強かった」ということに尽きる。
田中としては序盤からガンガンと圧力をかけ、早いランドで仕留めようという作戦だったと思う。
しかし、パランポンの思わぬ反撃にあいダウンを喫した。
2ラウンド、3ラウンドあたりから田中が作戦を変えていく。
本来の器用さを見せ始める。
左ジャブから、左アッパー、左だけでも多彩なるバリエーションのパンチを繰り出す。
序盤には見せなかった変幻自在のフットワーク。
パランポンは「でんでん太鼓」である。
軸がぶれずに、その軸を中心としてコンパクトなフック、ストレートを素早い回転によって繰り出している。
パランポンのパンチの出し方を見て私は感心していた。
では、パランポンを攻略するためにはどうすればいいのか?
でんでん太鼓はターゲットが定まり、それに向かって軸が定まった時に威力を発揮する。
となればターゲットを定めさせなければいい。
序盤、田中は仕留めるためにと至近距離、しかも同じポジションに立ち続けていた。
だからパランポンのパンチを浴びることになった。
田中に必要だったのは左右の動きである。
同じ位置に固定せず、左右にステップワークで身体を動かす。
こうなればパランポンは的を絞れなくなりパンチを出すことさえ難しくなってしまう。
田中は中盤に差しかかるあたりでこれに気づいた。
縦の動きよりも横の動き。
横の動きの中で繰り出す多彩なるパンチの打ち分け。
田中が試合の流れを自分のもとへと引き寄せていく。
8ラウンド、田中は手をとめ、パランポンの攻撃をフットワークでかわし続けた。
パランポンの攻撃のパターン、パンチの軌道、これらをしっかりと読むことができたようだ。
9ラウンド、衝撃が走る。
パランポンが倒れた。
立ち上がった時には、すでに身体に力が入っていない。
田中が一気に出る。
多彩なコンビネーションでラッシュ。
レフェリーが試合をとめた。
9ラウンド、TKOでの勝利。
田中が予想外に苦戦した。
緊迫した試合内容。
エンターテイメントとして見る分にはおもしろい試合であったように思う。
リングサイドにはWBA王者・田口がいた。
田中としては、田口にプレッシャーをかけるためにも「圧勝」して防衛したかったことだろう。
世界王者が乱立するボクシング界。
ただの王者でいたのでは評価されない。
誰とやるのか、どういう試合をするのか。
内容が問われるのだ。
日本人対決。
TBSの中継では過去に行われた3試合の映像が流れた。
薬師寺vs辰吉、畑山vs坂本、井岡vs八重樫、
どれも壮絶なる打ち合いであった。
人々の記憶に残り続ける名勝負であったと言えるだろう。
井岡vs八重樫に続く、日本人同士による団体統一戦の実現はなるのか。
試合後、田中は頭痛を訴え、大事をとって病院に向かったそうだ。
国内最短記録で世界王者、2階級制覇、天才が味わった思わぬ苦戦。
喫したダウン、腫れ上がった瞼、そして流血。
この悔しさが、天才をさらに覚醒させていくことになるだろう。
田中vs田口、ぜひ実現させてほしい。
楽しみである。
WBC世界バンタム級タイトルマッチ
王者・山中慎介 vs 挑戦者・ルイス・ネリ
2017.8.15 京都・島津アリーナ京都
13回連続防衛。
この試合で具志堅用高に並ぶ予定であった。
日本ボクシング界にとっても大きな意味を持つ試合になる予定であったはず…。
1ラウンド。
山中の立ち上がりが良い。
鋭い右のジャブ、そこから伸びていくストレート。
フック系のパンチが主体のネリとしては中間距離に立ちたいが、山中はそこよりも若干遠い位置をキープしている。
ネリに距離を詰めさせない。
そして左ストレートを狙い続けながら、右のリードパンチを鋭く放っていく。
山中に勢いがある。
2ラウンド~3ラウンド。
ネリの連打が放たれた。
しかし、ネリのパンチにはそれほどの脅威は感じない。
ここで試合後の山中のコメントを差し込んでみたいと思う。
「負けてこんなこと言うのはなんですけど、大したことない。
これならいけると思った。
ジャブも当たっていたし、左も狙いやすかった。距離も戦いやすかった。」
これが山中の正直な感想だろう。
同じフック系のパンチで攻め込んできたモレノの方がよっぽどこわかった。
山中もネリに対してはある程度の余裕を持ちながら対応できていたと思う。
山中はスロースターターである。
序盤の点数を取りこぼすことは想定内。
パンチをもらってもドスンと響くような衝撃はないし、危険なパンチをモロに喰らうということもなかった。
4ラウンド。
ネリに連打を許す。
ものすごい勢いで山中が崩れていった。
打たれ弱い。
身体そのものに力が入っていない。
大和心トレーナーがタオルを投げると同時にリングに入っていく。
山中のTKO負け。
今回のように、レフェリーが試合を続行させようとしている中でセコンドがタオルを投げるというシーンはあまり見られない。
まして、これは世界戦のリングである。
このタオル投入が物議を醸す結果となった。
大和トレーナーがタオルを投げる際、他のセコンド陣への相談がなかったのだ。
山中が所属する帝拳ジムの本田会長は「(トレーナー)個人の感情が入った。最悪なストップ。ビックリした。山中も納得してないだろう。」と激怒。
たしかに4ラウンド(タオル投入)まで山中はダウンをしていない。
解説席にいた具志堅用高も「タオルが早い…」と言った。
ただ、私はタオルが早いとは思わなかった。
ここ2年ほど、山中は明らかな衰えを見せ始めていた。
前回のカルロス・カールソン戦。
強敵・モレノを豪快なKOで退けた山中にとって、カールソンは明らかな格下である。
早々に試合を決めてしまうのではないか、多くの人がそう思っていただろうが結果は違った。
カールソンの反撃に遭いヒヤリとさせられる場面が作り出されてしまったのだ。
これは相手とは関係のない山中自身の問題である。
「ダウン癖」がついてしまっている。
ここ数試合、山中がダウンを喫する場面をみることが多くなった。
相手のパンチを被弾することは仕方がないが、以前の山中であれば何の問題もなかった場面でグラついてしまう。
山中の攻撃力は試合を重ねるごとにレベルが上がっていた。
神の左は進化している。
この打たれ弱さを、磨きをかけたオフェンス力で何とかカヴァーして勝ち続けていたのだ。
これについては山中本人が一番わかっていたはず。
試合後のコメントであることが語られた。
「納得のいく勝ち方ができれば、それ(引退)でもいいのかなと思っていた。」
偉大なる具志堅用高の記録に並んだ時点で、もう幕を下ろしてもいい。
大和トレーナーともこの話し合いを持っていたのだろう。
大和トレーナーからすれば山中の第二の人生を考えた時、ここで肉体に深刻なダメージを負わせるべきではないと判断したのではないだろうか。
長年にわたって激闘を重ねてきた肉体は、もう悲鳴をあげている。
今年の10月で35歳。
決して若くはない。
ボクシングはまさに命がけの勝負である。
万が一、という危険が常に隣にある世界。
仮にまだ山中が若いとして、これが「命がけで世界のベルトを獲りにいく試合」ということであればタオルは投げなかっただろう。
しかし、山中は十分に戦ってきた。
素晴らしすぎるほどの実績も作った。
家庭には幼い子供が2人いる。
守っていかなければならない妻子、第二の人生を考えた時に、今後の試合によって万が一という事態が起こった時、それを山中自身が受け入れられるだろうか。
受け入れられるはずがない。
万が一は絶対にあってはならないのだ。
防衛を続ける中で頭の中に「引退」という文字がよぎるということは、もうピークは終わっている。
ここから劇的な進化を望むことは難しい。
経験とテクニックで、どうごまかしながら戦っていくか。
今回の試合、ネリが強かったというよりも山中が自ら崩れていったように思う。
本田会長も山中が望むのであればネリとの再戦を実現させるだろう。
山中の再起=ネリとのダイレクトリマッチ、であることは言うまでもない。
しかし、ここで再起をしたとして次の山中がどうなるのか。
先日、引退を発表した内山高志の姿が浮かぶ。
内山がKO負けした後に挑んだリマッチ。
KO負けの残像が脳にこびりついている。
勢い、気迫、エネルギー、すべてが失速していた。
山中の場合、ネリ以前の問題として「打たれ弱さ」を克服しなければならない。
強烈なパンチを被弾したわけでもない中で、身体から力が抜けヨロヨロとロープを背負うことになった。
これでは誰が相手でもこういう結果になってしまう。
山中からしても今回の試合は消化不良であったと思う。
山中のコメントにもそれは表れている。
「(TKOされた4Rについて)
そんなにもらっているつもりはなかったですし、大丈夫だったんですけどセコンドを心配させてしまった。
みなさんの期待に応えられなかったのが申し訳ない。
今後については何も考えられない。」
ネリに圧倒されたわけでもない。
自身の力をすべて出しきった満足感もない。
なぜ負けたのか?
それは肉体の衰えからくる打たれ弱さにある。
かつての山中は強かった。
ビッグ・ダルチニアンを退けた頃の山中がいれば、今回のネリなど何の問題もなかった。
夢ではあるがもう一度、めちゃくちゃに強い山中が見たい。
再起するのか?
少しの時間をかけて結論を出すのだろう。
山中の発表を待ちたいと思う。
王者・山中慎介 vs 挑戦者・ルイス・ネリ
2017.8.15 京都・島津アリーナ京都
13回連続防衛。
この試合で具志堅用高に並ぶ予定であった。
日本ボクシング界にとっても大きな意味を持つ試合になる予定であったはず…。
1ラウンド。
山中の立ち上がりが良い。
鋭い右のジャブ、そこから伸びていくストレート。
フック系のパンチが主体のネリとしては中間距離に立ちたいが、山中はそこよりも若干遠い位置をキープしている。
ネリに距離を詰めさせない。
そして左ストレートを狙い続けながら、右のリードパンチを鋭く放っていく。
山中に勢いがある。
2ラウンド~3ラウンド。
ネリの連打が放たれた。
しかし、ネリのパンチにはそれほどの脅威は感じない。
ここで試合後の山中のコメントを差し込んでみたいと思う。
「負けてこんなこと言うのはなんですけど、大したことない。
これならいけると思った。
ジャブも当たっていたし、左も狙いやすかった。距離も戦いやすかった。」
これが山中の正直な感想だろう。
同じフック系のパンチで攻め込んできたモレノの方がよっぽどこわかった。
山中もネリに対してはある程度の余裕を持ちながら対応できていたと思う。
山中はスロースターターである。
序盤の点数を取りこぼすことは想定内。
パンチをもらってもドスンと響くような衝撃はないし、危険なパンチをモロに喰らうということもなかった。
4ラウンド。
ネリに連打を許す。
ものすごい勢いで山中が崩れていった。
打たれ弱い。
身体そのものに力が入っていない。
大和心トレーナーがタオルを投げると同時にリングに入っていく。
山中のTKO負け。
今回のように、レフェリーが試合を続行させようとしている中でセコンドがタオルを投げるというシーンはあまり見られない。
まして、これは世界戦のリングである。
このタオル投入が物議を醸す結果となった。
大和トレーナーがタオルを投げる際、他のセコンド陣への相談がなかったのだ。
山中が所属する帝拳ジムの本田会長は「(トレーナー)個人の感情が入った。最悪なストップ。ビックリした。山中も納得してないだろう。」と激怒。
たしかに4ラウンド(タオル投入)まで山中はダウンをしていない。
解説席にいた具志堅用高も「タオルが早い…」と言った。
ただ、私はタオルが早いとは思わなかった。
ここ2年ほど、山中は明らかな衰えを見せ始めていた。
前回のカルロス・カールソン戦。
強敵・モレノを豪快なKOで退けた山中にとって、カールソンは明らかな格下である。
早々に試合を決めてしまうのではないか、多くの人がそう思っていただろうが結果は違った。
カールソンの反撃に遭いヒヤリとさせられる場面が作り出されてしまったのだ。
これは相手とは関係のない山中自身の問題である。
「ダウン癖」がついてしまっている。
ここ数試合、山中がダウンを喫する場面をみることが多くなった。
相手のパンチを被弾することは仕方がないが、以前の山中であれば何の問題もなかった場面でグラついてしまう。
山中の攻撃力は試合を重ねるごとにレベルが上がっていた。
神の左は進化している。
この打たれ弱さを、磨きをかけたオフェンス力で何とかカヴァーして勝ち続けていたのだ。
これについては山中本人が一番わかっていたはず。
試合後のコメントであることが語られた。
「納得のいく勝ち方ができれば、それ(引退)でもいいのかなと思っていた。」
偉大なる具志堅用高の記録に並んだ時点で、もう幕を下ろしてもいい。
大和トレーナーともこの話し合いを持っていたのだろう。
大和トレーナーからすれば山中の第二の人生を考えた時、ここで肉体に深刻なダメージを負わせるべきではないと判断したのではないだろうか。
長年にわたって激闘を重ねてきた肉体は、もう悲鳴をあげている。
今年の10月で35歳。
決して若くはない。
ボクシングはまさに命がけの勝負である。
万が一、という危険が常に隣にある世界。
仮にまだ山中が若いとして、これが「命がけで世界のベルトを獲りにいく試合」ということであればタオルは投げなかっただろう。
しかし、山中は十分に戦ってきた。
素晴らしすぎるほどの実績も作った。
家庭には幼い子供が2人いる。
守っていかなければならない妻子、第二の人生を考えた時に、今後の試合によって万が一という事態が起こった時、それを山中自身が受け入れられるだろうか。
受け入れられるはずがない。
万が一は絶対にあってはならないのだ。
防衛を続ける中で頭の中に「引退」という文字がよぎるということは、もうピークは終わっている。
ここから劇的な進化を望むことは難しい。
経験とテクニックで、どうごまかしながら戦っていくか。
今回の試合、ネリが強かったというよりも山中が自ら崩れていったように思う。
本田会長も山中が望むのであればネリとの再戦を実現させるだろう。
山中の再起=ネリとのダイレクトリマッチ、であることは言うまでもない。
しかし、ここで再起をしたとして次の山中がどうなるのか。
先日、引退を発表した内山高志の姿が浮かぶ。
内山がKO負けした後に挑んだリマッチ。
KO負けの残像が脳にこびりついている。
勢い、気迫、エネルギー、すべてが失速していた。
山中の場合、ネリ以前の問題として「打たれ弱さ」を克服しなければならない。
強烈なパンチを被弾したわけでもない中で、身体から力が抜けヨロヨロとロープを背負うことになった。
これでは誰が相手でもこういう結果になってしまう。
山中からしても今回の試合は消化不良であったと思う。
山中のコメントにもそれは表れている。
「(TKOされた4Rについて)
そんなにもらっているつもりはなかったですし、大丈夫だったんですけどセコンドを心配させてしまった。
みなさんの期待に応えられなかったのが申し訳ない。
今後については何も考えられない。」
ネリに圧倒されたわけでもない。
自身の力をすべて出しきった満足感もない。
なぜ負けたのか?
それは肉体の衰えからくる打たれ弱さにある。
かつての山中は強かった。
ビッグ・ダルチニアンを退けた頃の山中がいれば、今回のネリなど何の問題もなかった。
夢ではあるがもう一度、めちゃくちゃに強い山中が見たい。
再起するのか?
少しの時間をかけて結論を出すのだろう。
山中の発表を待ちたいと思う。
NEWSポストセブンの記事より抜粋して引用させていただく。
「不可解な判定」でWBA世界ミドル級タイトルマッチに敗れたロンドン五輪金メダリストの村田諒太(31)。ファンの間には落胆が渦巻いているが、意外にも「村田の商品価値は上がった」と見るボクシング関係者は少なくない。
「これまで村田は元五輪金メダリストという肩書きはあったものの、世界トップクラスの選手と対戦したことがなかったため、ボクシング関係者は彼の真の実力を測りかねていた。だが、今回のアッサン・エンダムとの一戦で世界でも勝てる実力を証明した上に、敗れたとはいえ、“疑惑の判定に泣いた”という物語まで付いた。商品価値は跳ね上がっており、ケタ違いのカネが動く米国のショービジネス界も放ってはおかないでしょう」(スポーツ紙記者)
「エンダムと再戦すれば、因縁の対決だけに興行規模は大きく膨らむ。総額5億円といわれた今回のファイトマネーを大きく上回る可能性は高い。試合で“恐るるに足らず”とわかった相手だけに、負けるリスクも少ない」
だが、それ以上にビッグマネーを掴むチャンスがある。WBCでの世界戦だ。現WBC王者のゲンナジー・ゴロフキンは37勝(33KO)無敗の怪物王者として君臨。今年9月に予定される人気ボクサーのサウル・アルバレスとの一戦はファイトマネーだけで総額20~30億円といわれている。ボクシングライターの原功氏が語る。
「村田がWBCに挑戦すれば、今秋以降にどちらかとの対戦が濃厚となる。勝てる見込みはともかく、本場・米国で“超ビッグネーム”と対戦すれば、村田にはファイトマネー、放映権収入など、全てを含めると10億円を超える大金が転がり込む可能性がある」
もし勝つことがあれば、米『フォーブス』誌が掲載するスポーツ選手の長者番付に一気にランクインする可能性も見えてくる。
すでに村田の元には、WBC会長からタイトルマッチのオファーが届いているという。涙を飲んだ「不可解判定試合」は、実は村田にとって“塞翁が馬”だったのかもしれない。
※週刊ポスト2017年6月9日号
以前よりWBAは商業主義の色が強く批判の対象となっている。
1番の問題点は、スーパー王者、正規王者、暫定王者と1つの団体で3人もの王者を同時に存在させタイトルマッチを連発してきたことだ。
世界王者を乱立させてしまえば王者そのものの権威を損なわせる。
タイトルマッチを連発したがる理由は金儲け以外の何ものでもない。
現在でこそ1階級につき1王者という動きを見せ始めているが、帝拳の本田会長がWBAでの世界戦を避けてきた理由がここにある。
仮に今回のタイトルマッチで村田が勝って世界王者になったとしても、スーパー王者はゴロフキンである。
竹原慎二以来となるミドル級での世界王者が誕生したと騒いだとしても、実際はWBAの中でさえトップには立てていないという状況。
WBAだけで世界王者が2人、そこに加えてWBC、IBF、WBOと1階級につき5人の世界王者が同時に存在しているのだ。
今となっては「世界王者」とは何か?
ここに疑問を感じざるを得ない。
ボクシングの世界もショービジネスであるのだから常にマネーになる選手を求めている。
エンダムvs村田の一戦は皮肉なことに「不可解な判定」という結末に終わったことで世界の注目を集めることになった。
すんなりと村田が王者になっていれば、ここまで騒がれることはなかっただろう。
またエンダムと拮抗した試合を見せたことにより、村田がミドル級の世界トップレベルであることが証明されている。
「疑惑の判定に泣いた元五輪金メダリスト」という肩書。
そしてエンダムとのリマッチを行ったとして、それに勝てばまさに「ミドル級に現れたニューヒーロー」となる。
村田はテレビの取材にて「現役を続行したい」と語っている。
エンダムとのリマッチか、WBCへの挑戦か、それともWBOか。
日本人がミドル級において世界挑戦への切符を手にすることは至難の業であると思われてきた。
しかし、村田の商品価値が跳ね上がったことにより、むしろ村田の方が主導する形で試合を選べるような立場になってきている。
村田vsゴロフキンは実現するのか。
動向に注目していきたい。
「不可解な判定」でWBA世界ミドル級タイトルマッチに敗れたロンドン五輪金メダリストの村田諒太(31)。ファンの間には落胆が渦巻いているが、意外にも「村田の商品価値は上がった」と見るボクシング関係者は少なくない。
「これまで村田は元五輪金メダリストという肩書きはあったものの、世界トップクラスの選手と対戦したことがなかったため、ボクシング関係者は彼の真の実力を測りかねていた。だが、今回のアッサン・エンダムとの一戦で世界でも勝てる実力を証明した上に、敗れたとはいえ、“疑惑の判定に泣いた”という物語まで付いた。商品価値は跳ね上がっており、ケタ違いのカネが動く米国のショービジネス界も放ってはおかないでしょう」(スポーツ紙記者)
「エンダムと再戦すれば、因縁の対決だけに興行規模は大きく膨らむ。総額5億円といわれた今回のファイトマネーを大きく上回る可能性は高い。試合で“恐るるに足らず”とわかった相手だけに、負けるリスクも少ない」
だが、それ以上にビッグマネーを掴むチャンスがある。WBCでの世界戦だ。現WBC王者のゲンナジー・ゴロフキンは37勝(33KO)無敗の怪物王者として君臨。今年9月に予定される人気ボクサーのサウル・アルバレスとの一戦はファイトマネーだけで総額20~30億円といわれている。ボクシングライターの原功氏が語る。
「村田がWBCに挑戦すれば、今秋以降にどちらかとの対戦が濃厚となる。勝てる見込みはともかく、本場・米国で“超ビッグネーム”と対戦すれば、村田にはファイトマネー、放映権収入など、全てを含めると10億円を超える大金が転がり込む可能性がある」
もし勝つことがあれば、米『フォーブス』誌が掲載するスポーツ選手の長者番付に一気にランクインする可能性も見えてくる。
すでに村田の元には、WBC会長からタイトルマッチのオファーが届いているという。涙を飲んだ「不可解判定試合」は、実は村田にとって“塞翁が馬”だったのかもしれない。
※週刊ポスト2017年6月9日号
以前よりWBAは商業主義の色が強く批判の対象となっている。
1番の問題点は、スーパー王者、正規王者、暫定王者と1つの団体で3人もの王者を同時に存在させタイトルマッチを連発してきたことだ。
世界王者を乱立させてしまえば王者そのものの権威を損なわせる。
タイトルマッチを連発したがる理由は金儲け以外の何ものでもない。
現在でこそ1階級につき1王者という動きを見せ始めているが、帝拳の本田会長がWBAでの世界戦を避けてきた理由がここにある。
仮に今回のタイトルマッチで村田が勝って世界王者になったとしても、スーパー王者はゴロフキンである。
竹原慎二以来となるミドル級での世界王者が誕生したと騒いだとしても、実際はWBAの中でさえトップには立てていないという状況。
WBAだけで世界王者が2人、そこに加えてWBC、IBF、WBOと1階級につき5人の世界王者が同時に存在しているのだ。
今となっては「世界王者」とは何か?
ここに疑問を感じざるを得ない。
ボクシングの世界もショービジネスであるのだから常にマネーになる選手を求めている。
エンダムvs村田の一戦は皮肉なことに「不可解な判定」という結末に終わったことで世界の注目を集めることになった。
すんなりと村田が王者になっていれば、ここまで騒がれることはなかっただろう。
またエンダムと拮抗した試合を見せたことにより、村田がミドル級の世界トップレベルであることが証明されている。
「疑惑の判定に泣いた元五輪金メダリスト」という肩書。
そしてエンダムとのリマッチを行ったとして、それに勝てばまさに「ミドル級に現れたニューヒーロー」となる。
村田はテレビの取材にて「現役を続行したい」と語っている。
エンダムとのリマッチか、WBCへの挑戦か、それともWBOか。
日本人がミドル級において世界挑戦への切符を手にすることは至難の業であると思われてきた。
しかし、村田の商品価値が跳ね上がったことにより、むしろ村田の方が主導する形で試合を選べるような立場になってきている。
村田vsゴロフキンは実現するのか。
動向に注目していきたい。
WBA世界ミドル級タイトルマッチ、
アッサン・エンダムvs村田諒太の一戦。
試合後、「疑惑の判定」と国内外を問わずに騒がれている。
エンダムの母国、フランスでも「村田が有利であった」との報道がなされた。
この騒動を受け、
WBAのヒルベルト・ヘスス・メンドサJr会長が正式にエンダムと村田の再戦を命じた。
しかも、ダイレクトリマッチである。
また、村田に負けの採点を下した2人のジャッジ、グスタボ・パディージャ(パナマ)、ヒューバート・アール(カナダ)の両名を6ヶ月の資格停止処分とした。
ここまで異例の展開を見せている。
世論も、メンドサ会長も、「村田が勝っていた」との見解を示しているが、
これをエンダム側はどう見ているのだろうか。
私が個人的に評価しているボクシング・ビート米国通信員、三浦勝夫氏の記事から抜粋して引用させていただく。
誰もが勝利を疑わず、大方は大差の判定勝ちと見た村田諒太(帝拳)のWBA世界ミドル級タイトルマッチ。2-1判定勝利に浴したアッサン・エンダム(フランス)のキューバ人トレーナー、ペドロ・ディアスを電話で直撃。エンダム陣営から見た疑惑の一戦を語ってもらった。
――エンダムはあなたが期待したような試合を見せたでしょうか?
ディアス(以下Dと略)「シー(イエス)。アッサンは作戦どおり戦ったと思う。作戦とは距離をとり、ジャブを突いて戦うことだった。ただ想像以上に村田が強いボクサーで前進してパンチを放ってきた。だから12ラウンズを通じて脚を止めてはいけない、ジャブを放ってガードを上げろと指示したんだ。村田は効かせるパンチを持っていたし多くの分野でいい仕事をしたけど、唯一欠点を挙げると手数が不足していた」
――ジャッジのスコアカードに関して。
D「試合は接戦だった。アッサンも村田もジムの練習の成果を発揮したと思う。でもボクシングは一撃で勝つことは難しい。そこが村田に味方しなかった・・・」
――それでもエンダムを支持した2人のジャッジは批判されています。
D「今回のスコアを批判する者はボクシングを知らない。同じく決定的なものを見逃している。プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」
――米国のボブ・アラム・プロモーターはエンダムが獲ったラウンドは2つだけと言ってますが。
D「村田に勝ってもらい、次戦をプロモートしたい思惑があったからだろう。アラムはビジネスの視野でしかボクシングを考えていない。とても痛ましいね。彼がプロモートしたパッキアオvsブラッドリー(第1戦=ティモシー・ブラッドリーが論議を呼ぶ2-1判定勝ち)の採点だって相当ヒドかったのに」
――今回、エンダム・サイドにもジャッジを選択できる権利があったのですか?
D「ノー。すべてWBAのヒルベルト・メンドサJr(会長)チームが任命した。なのにあの声明だ。(注:「正当な判定を提供できず、怒りと不満を感じる。私のスコアは117-110で村田の勝利」とツイート)彼もとても恥ずかしい。アラム同様ビジネスのことしか頭にないんだ」
ここでJBC(日本ボクシング・コミッション)が採点の内容に関してメンドサJr会長に文書で抗議したことを聞こうとした。しかしディアス氏はそれを遮るようにメンドサ氏へ悪態をつき始めた。「WBAは我々をサポートする立場にありながら逆にこちらをおとしめようとしている。その会長は尊敬すべき存在だが、今回の件は会長の行動ではない。職務の責任を感じてしまう」(ディアス氏)。そして「タイトル認定団体で過去に今回のような言動を取った者は一人もいない。パッキアオvsブラッドリーの判定問題の時、当時のWBCホセ・スライマン会長は一切、関与しなかった」とまくし立てた。
――最終回が終了した時点でエンダムの勝利を確信しましたか?
D「試合はクロスファイトで、向こう(村田)は日本のファンの絶大な応援があった。22年ぶりのミドル級王者誕生の期待感、オリンピック金メダリストの背景、プロモーターはミスター本田(帝拳ジム本田明彦会長)、地元コミッション・・・とこちらは状況が不利だった。でもアッサンは試合を通じてテクニックを披露したからジャッジに支持されても不思議ではないと信じていた。アッサンは(勝利へ)手順を踏んだ。その点、村田はダウンを奪った後、それが実行できなかった。ジャッジたちはいいスコアを記したと評価している」
――村田のボクシングにはどんな印象を持ちましたか?
D「卓越したボクサーでコンプリートな選手に近いと感じた。繰り返すけど唯一、不足していたのが手数だった。彼を祝福したいし、日本のコミッションが取った行動もこちらは受け入れる」
――今回の判定問題でエンダムが精神的に落ち込むことはないですか?
D「それは全くない。彼は試合に勝ったんだから。精神的にダメージを受けたのは村田の勝利を主張する人々だろう」
――もし村田が勝利者だったら、エンダム陣営は逆に抗議していたでしょうか?
D「それはわからない。慎重に対処する動きになっただろう。でも一度下った判定が覆ることは絶対ない。もしそんな不幸な事態になったら、弁護士を立ててWBAを提訴する覚悟だ」
――エンダムの次の相手は?村田とのダイレクト・リマッチの可能性は?
D「状況を見極めながらベストな相手を選びたい。村田とのリマッチは契約に入っていない。でも明日にもこちらは応じられる。ジャッジもメンドサが任命して構わない。でも場所はフランスだ」
ディアスが語った内容で気になった点が2つ。
1つは、「WBAは我々をサポートする立場にありながら逆にこちらをおとしめようとしている。その会長は尊敬すべき存在だが、今回の件は会長の行動ではない。職務の責任を感じてしまう」(ディアス氏)。そして「タイトル認定団体で過去に今回のような言動を取った者は一人もいない。パッキアオvsブラッドリーの判定問題の時、当時のWBCホセ・スライマン会長は一切、関与しなかった」とまくし立てた。
現チャンピオンはエンダムである。
本来であればWBAはエンダムを保護しなければならない。
メンドサ会長が「村田の圧勝であった」との意見を述べた場合、エンダムの立場はなくなってしまう。
2つめ。
ディアスから見たこの試合における村田の印象について。
「村田は効かせるパンチを持っていたし多くの分野でいい仕事をしたけど、唯一欠点を挙げると手数が不足していた」
「試合は接戦だった。アッサンも村田もジムの練習の成果を発揮したと思う。でもボクシングは一撃で勝つことは難しい。そこが村田に味方しなかった・・・」
「今回のスコアを批判する者はボクシングを知らない。同じく決定的なものを見逃している。プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」
「卓越したボクサーでコンプリートな選手に近いと感じた。繰り返すけど唯一、不足していたのが手数だった。彼を祝福したいし、日本のコミッションが取った行動もこちらは受け入れる」
村田がKOで倒してしまえば何の問題もなかった。
あるいは2度、3度とダウンを奪っていれば良かったのだ。
手数を少なくして一撃を狙う。
これで倒せれば問題はない。
しかし判定までいった場合、これに疑問符がついても仕方がない。
まさに「プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」 ということになるのではないだろうか。
皮肉なことに、この敗戦により村田は世界的な知名度を得ることができた。
現にWBO、WBCからオファーがきている。
エンダム戦で村田が世界ミドル級のトップ選手であるということが証明された。
世界はゴロフキンに続くミドル級のスターを必要としている。
村田がこの最前線に躍り出る可能性は十分にある。
また、エンダムと村田のダイレクトリマッチが実現すれば世界が注目する一戦になることは間違いない。
今後の展開に注目したい。
アッサン・エンダムvs村田諒太の一戦。
試合後、「疑惑の判定」と国内外を問わずに騒がれている。
エンダムの母国、フランスでも「村田が有利であった」との報道がなされた。
この騒動を受け、
WBAのヒルベルト・ヘスス・メンドサJr会長が正式にエンダムと村田の再戦を命じた。
しかも、ダイレクトリマッチである。
また、村田に負けの採点を下した2人のジャッジ、グスタボ・パディージャ(パナマ)、ヒューバート・アール(カナダ)の両名を6ヶ月の資格停止処分とした。
ここまで異例の展開を見せている。
世論も、メンドサ会長も、「村田が勝っていた」との見解を示しているが、
これをエンダム側はどう見ているのだろうか。
私が個人的に評価しているボクシング・ビート米国通信員、三浦勝夫氏の記事から抜粋して引用させていただく。
誰もが勝利を疑わず、大方は大差の判定勝ちと見た村田諒太(帝拳)のWBA世界ミドル級タイトルマッチ。2-1判定勝利に浴したアッサン・エンダム(フランス)のキューバ人トレーナー、ペドロ・ディアスを電話で直撃。エンダム陣営から見た疑惑の一戦を語ってもらった。
――エンダムはあなたが期待したような試合を見せたでしょうか?
ディアス(以下Dと略)「シー(イエス)。アッサンは作戦どおり戦ったと思う。作戦とは距離をとり、ジャブを突いて戦うことだった。ただ想像以上に村田が強いボクサーで前進してパンチを放ってきた。だから12ラウンズを通じて脚を止めてはいけない、ジャブを放ってガードを上げろと指示したんだ。村田は効かせるパンチを持っていたし多くの分野でいい仕事をしたけど、唯一欠点を挙げると手数が不足していた」
――ジャッジのスコアカードに関して。
D「試合は接戦だった。アッサンも村田もジムの練習の成果を発揮したと思う。でもボクシングは一撃で勝つことは難しい。そこが村田に味方しなかった・・・」
――それでもエンダムを支持した2人のジャッジは批判されています。
D「今回のスコアを批判する者はボクシングを知らない。同じく決定的なものを見逃している。プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」
――米国のボブ・アラム・プロモーターはエンダムが獲ったラウンドは2つだけと言ってますが。
D「村田に勝ってもらい、次戦をプロモートしたい思惑があったからだろう。アラムはビジネスの視野でしかボクシングを考えていない。とても痛ましいね。彼がプロモートしたパッキアオvsブラッドリー(第1戦=ティモシー・ブラッドリーが論議を呼ぶ2-1判定勝ち)の採点だって相当ヒドかったのに」
――今回、エンダム・サイドにもジャッジを選択できる権利があったのですか?
D「ノー。すべてWBAのヒルベルト・メンドサJr(会長)チームが任命した。なのにあの声明だ。(注:「正当な判定を提供できず、怒りと不満を感じる。私のスコアは117-110で村田の勝利」とツイート)彼もとても恥ずかしい。アラム同様ビジネスのことしか頭にないんだ」
ここでJBC(日本ボクシング・コミッション)が採点の内容に関してメンドサJr会長に文書で抗議したことを聞こうとした。しかしディアス氏はそれを遮るようにメンドサ氏へ悪態をつき始めた。「WBAは我々をサポートする立場にありながら逆にこちらをおとしめようとしている。その会長は尊敬すべき存在だが、今回の件は会長の行動ではない。職務の責任を感じてしまう」(ディアス氏)。そして「タイトル認定団体で過去に今回のような言動を取った者は一人もいない。パッキアオvsブラッドリーの判定問題の時、当時のWBCホセ・スライマン会長は一切、関与しなかった」とまくし立てた。
――最終回が終了した時点でエンダムの勝利を確信しましたか?
D「試合はクロスファイトで、向こう(村田)は日本のファンの絶大な応援があった。22年ぶりのミドル級王者誕生の期待感、オリンピック金メダリストの背景、プロモーターはミスター本田(帝拳ジム本田明彦会長)、地元コミッション・・・とこちらは状況が不利だった。でもアッサンは試合を通じてテクニックを披露したからジャッジに支持されても不思議ではないと信じていた。アッサンは(勝利へ)手順を踏んだ。その点、村田はダウンを奪った後、それが実行できなかった。ジャッジたちはいいスコアを記したと評価している」
――村田のボクシングにはどんな印象を持ちましたか?
D「卓越したボクサーでコンプリートな選手に近いと感じた。繰り返すけど唯一、不足していたのが手数だった。彼を祝福したいし、日本のコミッションが取った行動もこちらは受け入れる」
――今回の判定問題でエンダムが精神的に落ち込むことはないですか?
D「それは全くない。彼は試合に勝ったんだから。精神的にダメージを受けたのは村田の勝利を主張する人々だろう」
――もし村田が勝利者だったら、エンダム陣営は逆に抗議していたでしょうか?
D「それはわからない。慎重に対処する動きになっただろう。でも一度下った判定が覆ることは絶対ない。もしそんな不幸な事態になったら、弁護士を立ててWBAを提訴する覚悟だ」
――エンダムの次の相手は?村田とのダイレクト・リマッチの可能性は?
D「状況を見極めながらベストな相手を選びたい。村田とのリマッチは契約に入っていない。でも明日にもこちらは応じられる。ジャッジもメンドサが任命して構わない。でも場所はフランスだ」
ディアスが語った内容で気になった点が2つ。
1つは、「WBAは我々をサポートする立場にありながら逆にこちらをおとしめようとしている。その会長は尊敬すべき存在だが、今回の件は会長の行動ではない。職務の責任を感じてしまう」(ディアス氏)。そして「タイトル認定団体で過去に今回のような言動を取った者は一人もいない。パッキアオvsブラッドリーの判定問題の時、当時のWBCホセ・スライマン会長は一切、関与しなかった」とまくし立てた。
現チャンピオンはエンダムである。
本来であればWBAはエンダムを保護しなければならない。
メンドサ会長が「村田の圧勝であった」との意見を述べた場合、エンダムの立場はなくなってしまう。
2つめ。
ディアスから見たこの試合における村田の印象について。
「村田は効かせるパンチを持っていたし多くの分野でいい仕事をしたけど、唯一欠点を挙げると手数が不足していた」
「試合は接戦だった。アッサンも村田もジムの練習の成果を発揮したと思う。でもボクシングは一撃で勝つことは難しい。そこが村田に味方しなかった・・・」
「今回のスコアを批判する者はボクシングを知らない。同じく決定的なものを見逃している。プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」
「卓越したボクサーでコンプリートな選手に近いと感じた。繰り返すけど唯一、不足していたのが手数だった。彼を祝福したいし、日本のコミッションが取った行動もこちらは受け入れる」
村田がKOで倒してしまえば何の問題もなかった。
あるいは2度、3度とダウンを奪っていれば良かったのだ。
手数を少なくして一撃を狙う。
これで倒せれば問題はない。
しかし判定までいった場合、これに疑問符がついても仕方がない。
まさに「プロは全ラウンドを通じてパンチを出し続けなければならない。単発でコンタクトするだけではダメだ」 ということになるのではないだろうか。
皮肉なことに、この敗戦により村田は世界的な知名度を得ることができた。
現にWBO、WBCからオファーがきている。
エンダム戦で村田が世界ミドル級のトップ選手であるということが証明された。
世界はゴロフキンに続くミドル級のスターを必要としている。
村田がこの最前線に躍り出る可能性は十分にある。
また、エンダムと村田のダイレクトリマッチが実現すれば世界が注目する一戦になることは間違いない。
今後の展開に注目したい。
Copyright© 2025 整体師・齊藤仁重オフィシャルサイト All rights reserved.